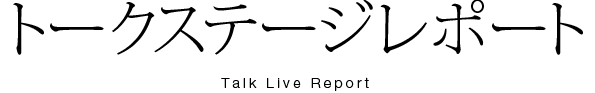

2016年6月23日(木)~26日(日)、東京・渋谷ヒカリエにて「東京カメラ部2016写真展」が開催されました。開催期間中のイベントステージでは、人気フォトグラファー、写真業界関係者、歴代東京カメラ部10選などをお招きして、さまざまなテーマでトークショーが行われました。
6月26日(日)に行われたパナソニックのトークショーでは、ハービー・山口さんにご出演いただき、LUMIX GX7 Mark II の「L.モノクローム」について、そしてハービー・山口さんの写真との向き合い方についてお話しいただきました。

まず、これまでにハービー・山口さんならではの、心温まる作品の数々がスライドショーで流されました。ライカで撮られたモノクロ作品が中心の構成です。

「いよいよ夏日といった感じで太陽が降り注いでいますが、よくいらっしゃいました。ざっと見て3万人くらいの方がここにいらっしゃいますね(笑)」

「スライドショーをご覧いただきました。オールモノクロなんですが、わたしはカラーよりは断然モノクロを撮ることが多いです。モノクロがゆえに強調できる光と影、表情、または構図、そういったものに魅せられて、仕事ではカラーですが、自分の作品では絶対モノクロだと思っている写真家です。洋服の色がわからないからじれったいとか、木が緑じゃないのが不自然だとかは思いません。モノクロはすっと入ってくるような感覚で、どことなくグルーヴが感じられる。そんなモノクロの良さを感じてくれたのなら、みなさんもモノクロモードでこれから撮ってみていただきたいです。作品のバリエーションが多くなると思います」
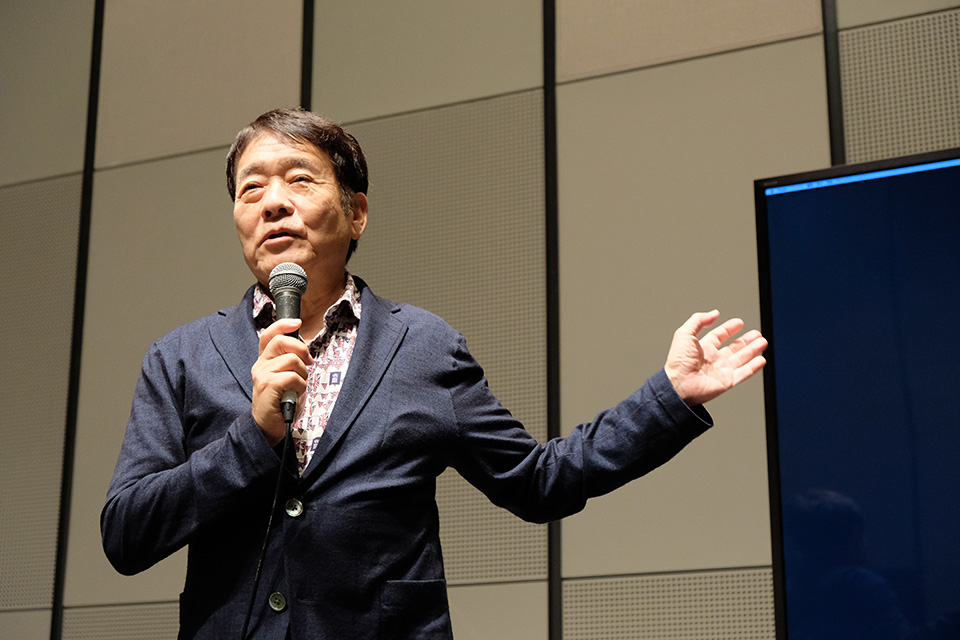
続いて、写真家生活をスタートするきっかけとなった若き日の渡英について語られました。
「ロンドンには23歳のときに行きました。親に旅費を借りて、半年間だけ行かせてくれと。できるだけ写真を撮ってきて、日本で個展をやって、フリーのカメラマンになれればな、という計算でした。日本の社会が敷いたレールに乗りはぐれてしまった人間でも生きていけるのか。そんな心境だったんです。サンタナというバンドの二代目のドラマーが新しいバンドを組んでイギリスに来ました。そして出会った。彼に聞いたんです。『なんでサンタナやめたんですか?サンタナにいたらお金も名誉もどんどん入ってくるじゃないですか』と。その答えは『人生はお金と名誉じゃないよ。自分の足で、自分の得意なものでどれだけ人生を築いて歩いていけるか、それを試すのも人生だろ。君はカメラでそれをしているんじゃないか。僕はドラムスティックでそれをしているんだ。僕も君も同じ人生を歩んでるんだよ』と。日本ではそんなことを言ってくれる人は一人もいなかった。イギリスでは、冒険だって人生だと。ロンドンの街が僕の背中を押してくれました」

「イギリスでは偶然色んなミュージシャンに出会いました。カルチャークラブというバンドのボーイ・ジョージとは一時期同じフロアに住んでいた時期もあります。この写真は、まだボーイ・ジョージと呼ばれる前ですね」

「この辺からボーイ・ジョージという存在がロンドンに知られるようになって、瞬く間にカルチャークラブは世界の人気バンドとなり、日本でも武道館でライブをやるようなバンドになりました」

「ジョージとは先週30年ぶりに再会し、これらの写真をデジタルプリントにしてプレゼントしました。昔の貧乏な頃の彼が写っています。つまり彼の原点が写っている。一夜にして名声と金を得たんじゃなくて、カルチャークラブを作り、女方を理解しない人から唾をかけられてもそれを曲げずにやってきた。初期の写真をプレゼントすることで、彼がロンドンに帰って、人生は金と名誉じゃないよということを感じて欲しいと思ったんです。友人や家族、街でスナップを撮ることは、その人の歴史の断片を撮っているということ。将来価値を生むかもしれないし、写真が思わぬ人の心に勇気をふりまくかもしれないんです」

作品とは、写真家になるということとは、などの定義についても、ハービー・山口さんならではの言葉で語られました。
「まず、写真はテーマ性と手法の二つが大切。テーマ性というのは、青い空を撮りたい、虹を撮りたい、女の子を撮りたい、などですね。そして、それをどういう手法で撮るのか。モノクロなのか、望遠レンズなのか、広角レンズなのか、フラッシュをたくのか、スナップなのか。テーマ性というのは、自分の心、これに興味があるぞというのに近ければ近いほど表現は強くなる。手法というのは、みんながやってるのと同じ手法でやったら目立たない。だから、自分なりの被写体へのアプローチというのが必要となり、その二つが結合した時に作品になります。つまり、この二つは自転車の前輪と後輪のように一対のものにして考えなくてはいけない。目立ちたいだけだと心がおいてきぼりで、名誉だけを求めてしまう。心に即したテーマを見つけないといけないわけですね。僕の論理では、写真家になる日はカメラを手に入れた日ではないんですね。本当に撮りたいものに出会った日です。すると自分の情熱が写真というものになると思います」

そして、LUMIX GX7 Mark IIの話題へと移ります。
「今からお見せするのはLUMIX GX7 Mark IIで撮った写真です。「L.モノクローム」というモードがあり、実に黒の締まりがいい。僕の写真はストレートなものが多いですが、このカメラがあることで、陰などを使った遊びができると感じました」

「これは女の子が窓辺に立っているんですが、ポスターフレームのプラスチックに映っているんです。遊びの部分を僕に教えてくれたのが『L.モノクローム』で、僕の新しい面を見せてくれました。これからの作家活動には大きなことじゃないかと思います。普通ならシルエットにせず女の子を明るく撮るけれど、シャドウにしたほうが形が出て面白いですよね」

「これはGX7の前機種であるGX8を使い、九州の門司で撮った写真です。モデルさんではなく人形を作るアーティストなんですが、とてもきれいな方だったので撮らせていただきました。これも、やはり光ですよね。フラッシュを焚いて光を回してしまったらドラマは出てこない。『L.モノクローム』ではないですが、モノクロ写真として良い一枚です」

「調子に乗って、彼女に階段まで降りてきてもらって、ガラスの内側に入ってもらい撮りました。ただストリートで撮るポートレートより遊びが入ってくるんですね」

ポートレートをうまく撮る心構えにも言及しました。
「よく僕の写真はあたたかいと言われます。では、どうやって撮るかというと、相手の幸せをそっと祈ってシャッターを切るんです。これは東日本大震災後の女川です。最初、僕は漁師さんの中に怖くて入っていけませんでした。でも、ずっと人間を撮ってきたカメラマンじゃないか。こうして全てを失ったところから立ち上がろうとする力強さを撮らないで、何を撮るんだ、と写真の神様が言うんです。だから、大声で『東京から写真を撮りに参りました。みなさんの復興にかけるお姿を世界に向けて発信するので撮らせてください!』と声を掛けて、早く復興してください、少しでも我々はみなさんを助けたいですという気持ちでシャッターを切りました。みなさんの幸せを祈ってこそ、何かで伝わるわけです」

「女川で撮らせてくれた青年は、ジョニー・ロットンのTシャツを来ていました。僕はジョニー・ロットンをロンドン時代に撮ったことがあり、その話題で盛り上がり友だちになりました。僕がロンドンにいた時代は、まさにパンクロック全盛の時代で、ジョニー・ロットンはセックス・ピストルズに在籍していて、もうひとつのビッグバンドのクラッシュのボーカルであるジョー・ストラマーを地下鉄で見掛けたことがあったんです。こんな偶然は二度とないと思い、勇気を出して撮らせてもらいました。そして、次の駅で彼が降りるとき、『撮りたいものは全て撮れよ、それがパンクだぞ』と言われて、ああ、パンクロックはそういうことなんだと思いました。
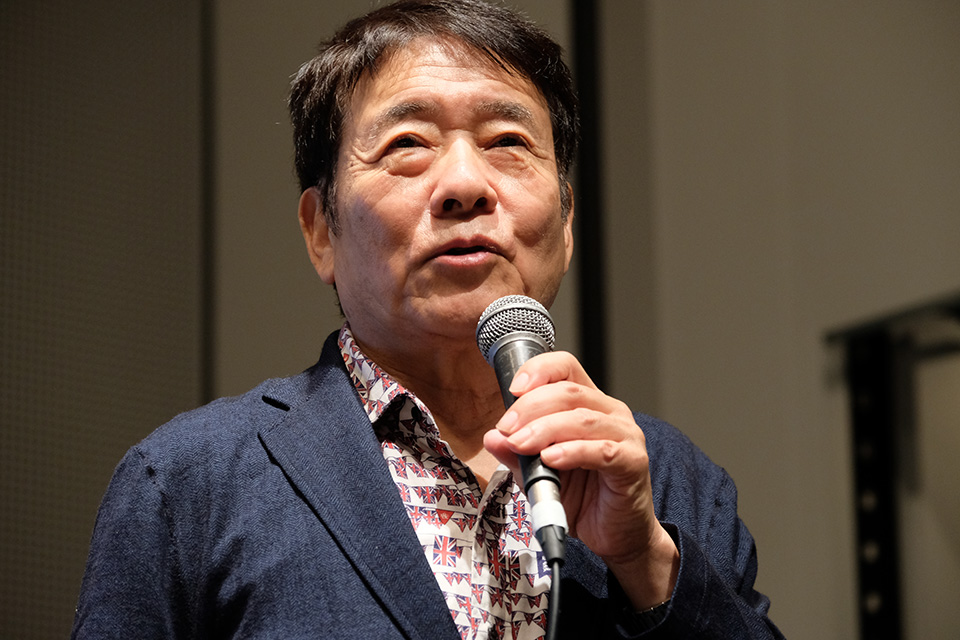
「去年の暮れ、ラジオのゲストに出たときに今の話をしたんですね。生放送が終わってから色々なメールがリスナーから届いたのですが、そのうちの一つが印象に残っています。『50歳、トラックドライバーです。運転中、ラジオから流れてきたパンクの話を聞いて、トラックを止めて泣きました。実は僕が20歳のとき、カメラマンになりたくてヨーロッパに行き何カ国も旅をし、日本に帰ってきて、やがて好きな人ができて結婚し、家族ができて、養うためにトラックドライバーになりました。僕は50歳になりましたが、いまの話を聞いて、もう一度カメラを握りたくなりました。50歳では遅くないですか?』と。僕は絶対遅すぎないと思うんです。ドライバーさんがGX7を買って、助手席に置き、助手席から見えた街の人生を撮ったらいいんじゃないか。トラックドライバーの目線で綴った人生論なんて世界に一冊もないです。決して遅いことなんてないです。先ほども言いましたが、写真家になる日はカメラを手に入れた日じゃないんです」

最後に、撮り始めた頃から現在まで、変わらぬ視点を持ち続けてることについて、印象深いエピソードを披露してくださいました。
「これは僕が写真家になりたいと思っていた20歳のころの写真です。公園を歩いていたら、バレーボールをやっている少女がいて、写真を撮らせてくださいと頼んだんです。僕があまりに一生懸命になっていたので、ボールが飛んできていることに気づかなかった。すると女の子が『危ない、よけて』と、ものすごく優しい目で僕をかばったんです。そのとき思ったんです。いまの優しい表情をもう一度どこかで見つけて撮りたい、と。あの表情が撮れたら、写真の力で世界は平和になる。翌年、その人に会いました。名前はさよさん。残念ながら、さよさんの写真はあまり残っていません。でも、何枚かが奇跡的に残っていて、この写真はそのうちの一枚です」

「そして最近、Facebookを見ていたら、さよさんに似ている方が目に留まり、DMを送り撮影をお願いしました。20歳の日に撮ったさよさん、2016年に撮ったその人。僕は常に20歳の目、心で撮っているんだなと思いました。アーティストというのは100歳になっても15歳の目で写真を撮ります。それが許されてる非常に特殊な職業なんです。僕は死ぬまで20歳の目で撮ると思います。いくら社会が変わろうが、家族が増えようが、みなさんの素晴らしい写真を撮るフレッシュな心を濁らすことなく、常に美しい人間のままで表現していってください。それは必ず困っている人に勇気を与えて地球を救う、それがアートの力だと信じて疑いません」