トークショーレポート
Talk Show Report
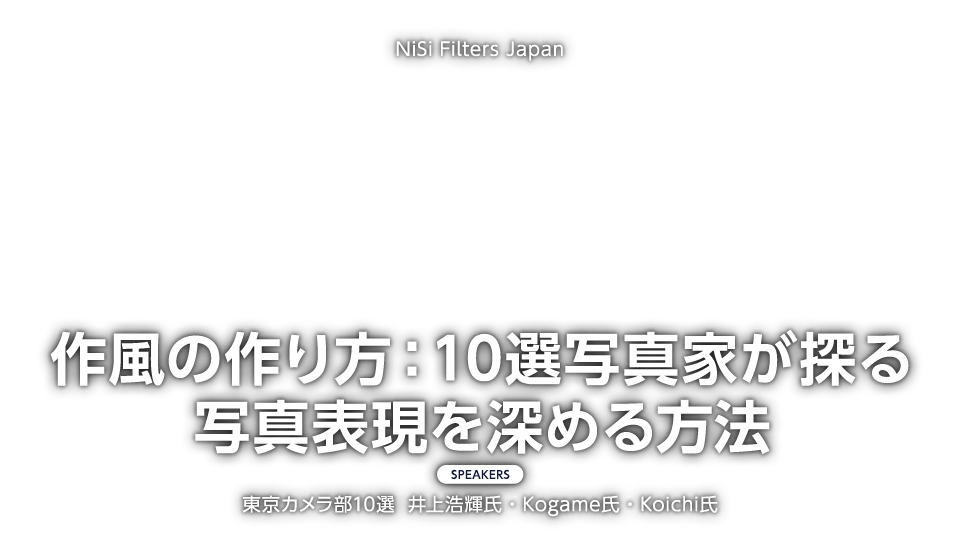
2024年9月20日(金)~9月23日(月・祝)、東京・渋谷ヒカリエにて「東京カメラ部2024写真展」が開催されました。開催期間中のイベントステージでは、人気フォトグラファー、写真業界関係者、歴代東京カメラ部10選などをお招きして、さまざまなテーマでトークショーが行われました。
9月23日(月・祝)に行われたNiSi Filters Japanのトークショーでは、東京カメラ部10選の井上浩輝氏、Kogame氏、Koichi氏にご登壇いただき、「作風の作り方:10選写真家が探る写真表現を深める方法」というテーマでお話しいただきました。
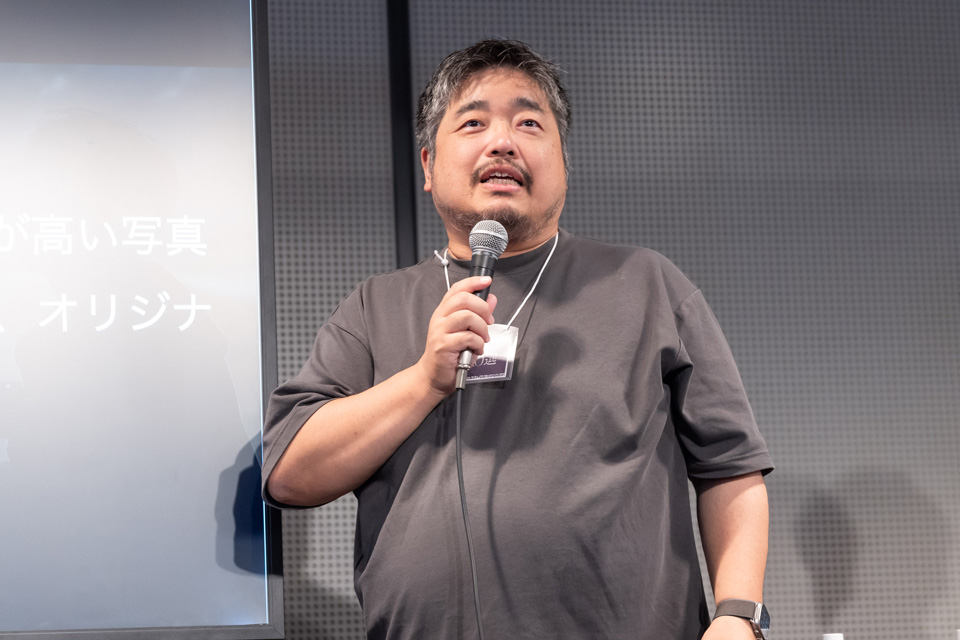
井上「みなさん、こんにちは。写真家の井上浩輝です。2014 年の東京カメラ部10選です。今日は『NiSi Filters Japan』のトークステージで『作風の作り方』ということをテーマにお話を聞いていきたいと思います。まず自己紹介を進めていきましょう。わたしは井上浩輝と申します。キツネを撮るということで有名になっていますが、実は早稲田大学で写真表現を教えております。いつの間にか大学教員になっていました。僕の立場からおふたりにどうやって作風というものを作っているのかということを聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします」

Kogame「2020年の東京カメラ部10選のKogameと申します。新潟を中心に活動しておりまして、写真はじめたのは2008年頃からになります。2022年に『International Photography Awards 2022』風景部門で『Nature Photographer Of the Year』を受賞しまして、その頃から写真に対する人生が変わってきているところで、内閣府からの依頼など写真活動を拡げていっています。井上さんとは新潟繋がりだったりしまして、本日も新潟のことなどをお話しできればいいなと思っております。よろしくお願いします」
井上「そう、僕は大学時代の4年間は新潟にいましたので、ちょっと懐かしいなと思いながらお写真を拝見しています。続いてKoichi君お願いします」

Koichi「はじめまして、Koichiと申します。岐阜県の飛騨高山市出身でいま29歳です。現在は東京で活動していて、主に風景の中に人物を入れ込んだポートレート作品を撮っています。おふたりとトークショーをするのは緊張しますが、よろしくお願いします」

井上「さて、いきなり文字が出てきて恐縮ですが、昨今、我々写真家たちの中で一番頭を悩ませている問題が、この『コモディティ化』です。さまざまな定義がありますが、ここでは写真発表時にはオリジナル性があって希少性が高い写真だったけれども、模倣した写真の発表が活性化した結果、オリジナルの市場価値が低下して一般的な写真になってしまうという悩ましいことを指しています。僕が写真家として動き出した時期は10年ほど前ですが、当時はもう少し穏やかにコモディティ化が進んでいたと思います。具体的には、僕の場合は2年ほど経つと似たような写真が出てきて、そこに似たような題名やキャプションが付いて、似たようなグッズが販売されてということが起きていましたが、いまは1週間や2週間、ヘタをすると数日で起きてしまっていることもあります。写真家にとって作風は命であるわけなんですね。もっとグロい言い方をすれば、生活の糧になっているわけです。でも。それがあっという間に似せたものが出てくると価格や価値が下がってしまう。僕らにとったらとてつもなく怖いことであり、追いかけられるならば、そのさらに先をと思うわけですが、これをみなさんがどうやって克服し、新しい表現を探していっているのかということを聞いてみたいと思います」

井上「今回、作品の独自性を視覚的、技術的、そして発表方法、さらにはそれらがどう一貫して継続され、多面的に展開されているのか、こんなところからお話を聞いてみたいと思います。みなさん、こんな感じで聞いてください。このふたりだからこそ、というものはどこにあるのか。彼らの作風作りというものを見ていければと思います。まず、視覚的という観点からおふたりの作品を見ていきます。Kogameさんは作品を考えるとき、視覚的特徴や見栄えというのを、どのように考えて展開されているのでしょう」

Kogame「わたしはもともと自然が大好きなんですね。しかし、さまざまなジャンルを撮ります。風景もポートレートも動物も撮りますが、なぜその被写体を撮るのかを意識して、敢えて広く撮る、ということをすごく意識しています」
井上「まず、ちょっと広め、という言葉が出てきました」
Kogame「たとえば、この只見線の写真ですが、鉄道メインの方だと鉄道を大きく撮ると思います。しかしわたしは、只見線が走る景色、後ろにあるのは日向倉山という名前なんですが、『倉』というのは山用語で『険しい』という意味なんですね。写真に山を入れることで、美しいだけでなく自然の厳しさもあるということを表したいと思い、すべてを入れた構図にしてみました。そして、これが視覚的な強さなのかなと思っております」
井上「この場所を知っている方にとってみると、ああ、ここを切り取ってきたんだなという楽しさがあるのはもちろんのこと、ちょっと引くことによって、この場所を語るということもできるでしょうし、僕自身はこの場所を自分の目ではまだ見たことがないのですが、Kogameさんが撮られている新潟のあちこちの風景というのは、自分が大学時代に見てきた風景でもあるので、少し引いた構図からは、懐かしさや共感性をもたらしてくれるのかなと思います。ではKoichiさんはいかがでしょう」

Koichi「わたしは色のバランスを気にして写真を撮っています。右側の写真は桜で有名な青森県の弘前公園で撮影した写真なんですけど、裾の色味にまで気をつけながら服を選んで撮影をしていて、その場所の景色に合った色のバランスを考えながら撮影をすることが多いです。左の写真も振り袖は紫色ですが、内側に赤が入っていて、風が吹いてひらっと赤が見えるときを狙って写真を撮っていて、色と配置のバランスにはこだわっていますね」
井上「色と配置、それをもう少し掘り下げていただいていいですか?」
Koichi「日の丸構図などさまざまな構図がありますが、どんな構図で撮るかは完全に感覚かなと思っています。ファインダーを見ていろいろと考えているうちに、自分がいちばん気持ちいいバランスが見えてきて、人の位置や枝の位置などもどんどん結論が出てきて、それを最終的に形にするように構成してくるという感じです」
井上「感覚的なお答えでしたが、僕もなんとなく感じるところがあるんです。構図にはさまざまなものがありますよね。3分割法の格子点に主題があったらいいよとか、そういう話があるとは思うんですけどれど、きっとそこから何らかの修正がおこなわれていると思うんです。その修正はKoichiさんの場合、おそらく全体のバランスの中で、例えば主役がちょっと重みがあるとき、脇役に軽さがあるときなど、その重さのバランス具合で、きっと何かが変わってくるだろうなというふうにわたしは聞いていました。そして、色という点でもKoichiさんの写真はとても特徴的だなと思っています。踏み込んでいいのかな? シャドウ部の色合いが特徴的だなということを感じています。見たものをそのまま表現するという方向性も写真にはあると思います。一方で見たものを、自分がこうだったらいいな、素敵だなという方向に少し振っていくというのも写真表現だと思います。Koichiさんのシャドウ部には『Koichiブルー』がありますよね。ちょっと緑がかったブルー。これ意識してるんですよね」

Koichi「はい、していますね。写真はハイライト部分とシャドウ部のバランスを取ることによって、立体感が出ると思っています。左の写真がわかりやすいと思いますが、アスファルトの部分がなんとなく青っぽい色味になってますよね」
井上「それ言っちゃうの?笑」
Koichi「編集をするときにシャドウとハイライトにそれぞれ色味を足すことができるのですが、そのときに少しずつ変化を出していくだけで、作品全体の雰囲気がガラッと変わって独自性に繋がっていきます。自分の好きな色、自分の作品にするために、ほんのちょっといじってあげるだけで全然違う雰囲気の写真に仕上がっていきます」
井上「すごくわかる。実はですね、僕の動物写真の中に出てくるアスファルトも少し青を入れています。あ、言っちゃった(笑)。アスファルトは人工物だから、ちょっと色味を変えても罪じゃないかな、なんて思って取り入れているんですが、ほんの少しアスファルトやコンクリートに青を入れると、かっこよく締まっていくんですよね」
Kogame「わたしは逆にアスファルトの色を抜いていますね」
井上「それもわかります! 背景の彩度を落とすのは効果的ですよね」
Kogame「主役に色があれば人間の視覚はそちらも向きます。主役に色で誘導をしておいて、見せたくない場所は彩度を落としたりぼかしたりするんです」
井上「もうひとつ今日大事なことがあって、それは1枚の写真が素敵に見えるコツというものです。そこには落差を作る、ということがあります。明るい暗いは大事だと思いますが、写真の中に彩度の高い低いがあるのも素敵なんです。例えば主役は彩度が高い、背景は彩度が低い。あとはピントが合っている、合っていないというのもあっていいと思うんですね。補色もあるかもしれないですし、概念の差、例えば男女でもいいですし大人と子どもでもいいかもしれない。こうやって落差を生むというのはすごく大事なんですね。いま僕は補色と言いましたけども、Koichiさんの写真のシャドウ部には『Koichiブルー』が入っているなんて言いましたけれど、ハイライトにもその反対、つまり補色のオレンジっぽさや黄色っぽさがありますよね」
Koichi「はい、ハイライトとシャドウのバランスを見ながら、ちょっとずつ、ちょっとずつ色味を足していくような感じで調整しています」
井上「この落差というものを、意図的に写真の中にそっと入れてあげる。どぎつく入れるのではなく、そっと入れてあげることで、作風の一部を構成していくのかなと思います」

Kogame「Koichiさんにお聞きしたいのですが、Koichiさんの写真を見ていると心地良いのです。悩み相談いいですか? わたしはさまざまなジャンルを撮るので、統一感を出しようがないんですよね。たとえば、全部同じ色味に合わせたら、その作品の良さも殺してしまうことも起こるのかなと思っていて、個々の作品を活かしつつ統一感を持たせるということは井上さんならどうしますか?」
井上「わたしがいちばん頭を悩ますのは航空会社の広告撮影なんですね。AIRDOの撮影をずっとしていますが、まずコーポレートカラーをずらしちゃいけないっていうことがあるので、そこは極力ずらさないようにします。もちろん、夕焼けの光りの中では少しずらすということも許されるとは思いますが。ではどこで井上らしさを作るかと言ったら、僕はさっき触れたように写真の中の差、特に明るさの差をちょっと大げさに作ってみるとか。ピントが合う、合わないをちょっと大げさにしてみるなど、写真の中に差を作るということをがんばっていますね。いま作っている写真群を減殺させない形で明るさにこだわり、彩度の違いなどを出すようにしています」
Kogame「なるほど、ありがとうございます」

井上「次は技術的なところにいってみましょうか。がんばっているところ、ちょっと手を混んで作っているところなどを、まずKogameさんからお願いできますでしょうか」
Kogame「実は技術的なことはあまり意識してないですね。事前に頭の中にイメージがあり、そのイメージに近づけるためにどういう選択をするのかというだけで、技術というのは手段でしかないと思っていますし、たいしたことはしてないんですよ。それぞれの組み合わせでしかない。例えばこの写真の場合、雪を映すためにストロボを焚いたりだとか、あと電車を止めるためにどうしようかと。このような薄暗い条件の中で電車を止めて写すのはかなりのシャッタースピードが必要になります。このときはたしか1/300秒や1/400秒なんですが、これだけ暗いと本来ノイズだらけなんです。最近はノイズリダクションが強力なので、現代だから撮れた写真という感じだと思います」

Kogame「PLフィルターはよく使いますね。わたしはRAWで撮影をしますが、ハイライト側の粘りというのが、どうしてもカメラのダイナミックレンジだけだと賄えないことがあるんです。特に反射の部分は白飛びをしがちなので、PLフィルターを使うことでそれを抑えることができます。また、空の色をしっかりと出したいとき。レタッチでもできないことはないですが、元の色が残っていると編集もとても楽なんです。そういう意味ではPLフィルターは風景撮影では必須だと思っています」


井上「僕はあまりPLフィルターを使えない状況なんです。ソニーの仕事をしていますので、レンズにガラスの板が入ってしまうと、おかしいなということになるので使えないんです。でも、いいぞ、いいぞ、とみなさんが言うので、飛行機の写真にならいいかなと思って使うようになってきました。そうすると気付いたんです。みなさん、PLフィルターって色被りしますよね? ちょっと緑になったり赤っぽくなったり。これをRAW現像で取り除くのはとても面倒ですし、JPEG撮って出しであれば絶望的です。これを直せるくらいであれば、そもそもPLフィルターを使わずに編集できてしまうと思うんですね。だからJPEG派の人ほど色被りをしないPLフィルターをちょっと高価でも使った方がいいです。最近、NiSi Filtersから発売されているPLフィルターを使っていて気付いたことがあります。肉眼や写真で撮ると、標高が低い位置の雲って灰色に写ったりすることがありません? あれPLフィルターを使って撮るとしっかり白く写るんです。そういう効果はありますよね」

井上「僕がKoichiさんの写真を見て気になることがあります。それは背景がとても整っているなと。CAさんを撮ることがあるので、さまざまなポートレートを見て研究をしていますが、Koichiさんの写真は背景の垂直と水平がとてもキレイに出ていますよね。僕もこれはとても気を付ける点なんです。空港の柱、空港の窓枠、飛行機の中の縦の線、横の線を整えて撮りたいなといつも思っているんですね。Koichiさんは気にしていますか?」

Koichi「僕はもともと風景を撮影していたということがあって、水準器を見ながら中心がどこか、どこが等分割になる位置なのかを意識しながら撮ることが多くなっているので、それがポートレートにも活きていると思います。視覚で見ているときは、カメラのファインダーで見ているときよりも全てにピントが合っているじゃないですか。その状態でモデルさんにピントを合わせ、背景はファインダー内ではボケていても真っ直ぐ整うように意識して撮っています」
井上「この丁寧さが見やすく、被写体やモデルさんが目に入ってくる写真になっているのかなと思います。他に気を付けている技術的なことはありますか?」

Koichi「ローアングル、ハイアングルから撮るというシーンがとても多いです。それはなぜかというと、先ほどお話しした構図やバランスと一緒なんですが、モデルさんの背景の色や条件などを見るようにしています。これをふつうに立った状態で真正面から撮ると、モデルさんが狙った場所に来ないんですよ。どうしてもモデルさんの背景を白くして目立たせたくて、踏み台に昇って、さらに手を上げてかなり高い位置が撮影をしています」

Koichi「逆に花火とともに撮るようなときは、リフレクションを狙うためにローアングルから撮影をしたりします。見る位置、撮る位置を変えながら撮るのはよく使う方法ですね」
井上「被写体を背景の中のどこに入れるのか。そして、背景は添えるものじゃなく、背景も撮るものというイメージがすごく強いんだろうなということを感じます。先ほど登壇したステージでお話ししたのですが、僕もキツネの写真を撮るとき、自分の身を隠してテントとかに入って撮るということはあまりしないんですね。それはなぜかというと、同じ空間の中に動物と一緒にいることを許してもらうんです。たいていは逃げていきますが、許してもらえれば、自分で好きなように動く可能性が出てくるんです。立ち膝で動くこともあるし、寝っ転がってゴロゴロと動くこともあるんですけども、そうやって自分が動くことで背景を調整しやすくするんです。単にキツネが写っているという写真よりも、背景がキレイな写真のほうがいいじゃないですか。背景も撮るという意識がすごく大事なんです」

井上「続いて発表方法についてです。何か気を付けていることはありますか? いまであればSNSが全盛ですから一般的だと思いますが、どんなSNSを選ぶのか。さまざまなものがある中で意識している点はありますか?」
Kogame「わたしはInstagramからはじめましたが、最近はXも中心にやっています。Instagramをはじめたときから、とにかくジャンルがバラバラで、先ほどもお話しした通り統一感がまったくなく。通常Instagramは統一感が大事で、それがないと伸びないと言われますよね。すごく悩んでいたのですが、そこにクオリティーという統一感を持たせようと思ったんです。それをやってから意外とフォロワー数が増えました。わたしはあまりコメントなどをしないのですが、ありがたいことです。Xでも同じように写真をクオリティー第一に考えて、そこは一貫させています」


Kogame「あとはフォトコンテストですね。特に海外のフォトコンテストに出すようにしていて、わたしは新潟が地元なんですけど、地元の景色が選ばれると、当然地元の方は喜びますし、観光協会の方も喜んでその写真を使わせてくださいという話も来たりしまして、そうすると地元に貢献しているなという気分にもなり、それが自分の楽しさにも繋がっています」
井上「海外のフォトコンテストをメディアとして使ってしまうというのはかっこいいですよね。さて、Koichiさんはフィルムでも撮っていますよね。それも発表方法のひとつに使うことに対してはいかがでしょう」
Koichi「デジタルで撮っている写真に関しては、もちろんInstagramなどSNSを中心に発表しています。ブースにもネガを置いていますが、デジタルで撮るのと、反対にデジタルに至るまでの過程として続いてきたフィルム文化を残したいという思いもあるので、フィルムカメラも使っています。撮らせていただいた方には、ネガの原版を持っていって見せる、ということが発表の形になっています。広い人たちに見せるということではSNSがもっとも効率的ですが、それ以上に実物を見てもらうことにもものすごく価値を感じているので、撮らせていただいた方にはネガを見せにいくということを大切にしています」

井上「デジタルがこれだけ普及した時代だからこそ、そのような見せ方が自分らしさになっているんですね。こうやって発表方法におふたりは気をつけています。さて、Kogameさんには一貫性・継続性について伺いましたが、Koichiさんはいかがでしょう」
Koichi「一貫性を出しやすいのがInstagramだと思います。Instagramは9マスで揃えたときに、とてもキレイなバランスを作ることができるんですね。それが純粋に楽しくて、明日はこの色の写真にしようかなとか、この次は花火を持ってくるとキレイに花火で五角形になるなとか考えていると、それがだんだんと楽しくなってきてしまって。9マスが揃ったときに、ああ気持ちいい、というのをひたすら続けているという感覚です。日課のようになっています」
井上「自分の作風を維持するためにフィルターを活用されているのを事前にお聞きしています。どのように活用されているかをKogameさんからよろしくお願いします」


Kogame「僕は撮れないものがないようにしたい、というタイプなんですね。だから新しいフィルターが発売されると使うようにしています。『Allure Soft』というフィルターがありまして、このフィルターを使うと、光があたった部分が拡散するような状態になります。これは娘なんですが、ふわっと幻想的な写真になっています。これはほぼ撮って出しに近い状態で、撮るだけでこのような表現ができるのは非常な個性だと思います。KoichiさんもAllure Softを使っていると思いますが、僕の写真と比べると、そこまでふわっとしていないじゃないですか。何かコツはあるんですか?」

Koichi「さっき事前に話したときに気付いたんですが、フィルターに当たっている光の強弱によってすごく細かく変化する点が、このフィルターの特徴だなと思いました。この写真は逆光の状態ですが、太陽が沈み終わった後の淡い光がフィルターに入っている状態で撮影をしたので、ちゃんと波のディテールは残っているんですね。パッと見たときにあまりふんわりしているとは思わないはずですが、ただよく見るとモデルさんの髪の毛のエッジ、髪の毛に入っている西日の部分はぼんやりと夕焼け色に染まっています。これはフィルターを外すと真っ黒のただの線になってしまいます。細かいこだわりですが、このように光の強弱でかなり左右されるなと思いました」
Kogame「なるほど、Allure Softを暗いところで使うと発想はなかったですね。このような明るさならブラックミストを使う方が多いと思いますが、ちょっと驚きました。こちらもかっこいいですよね」

Koichi「ありがとうございます。韓国で撮った写真ですが、まさにわかりやすい作例として出した写真で、左側は効果が出ている状態ですが、ふわっとしていることがわかりますよね。強い光を出している看板は効果が強めに出て、西日が沈んだ後のやんわりした光だとディテールを残しながら輝いてくれるフィルターです」
井上「このフィルターは光をすごく意識し、暗いところの中にある灯りを探し、そこを脇役でうまく使ってあげると、より素敵になるのかもしれませんね」

Koichi「この右側の写真を見ていただくとわかりやすいのですが、このようなシーンでブラックミストを使うと、提灯もふわっと拡散して外側にエッジができてしまいます。Allure Softはエッジがわざとらしく出るのではなく、でも弱い光にも反応してくれてディテールを残してくれます」
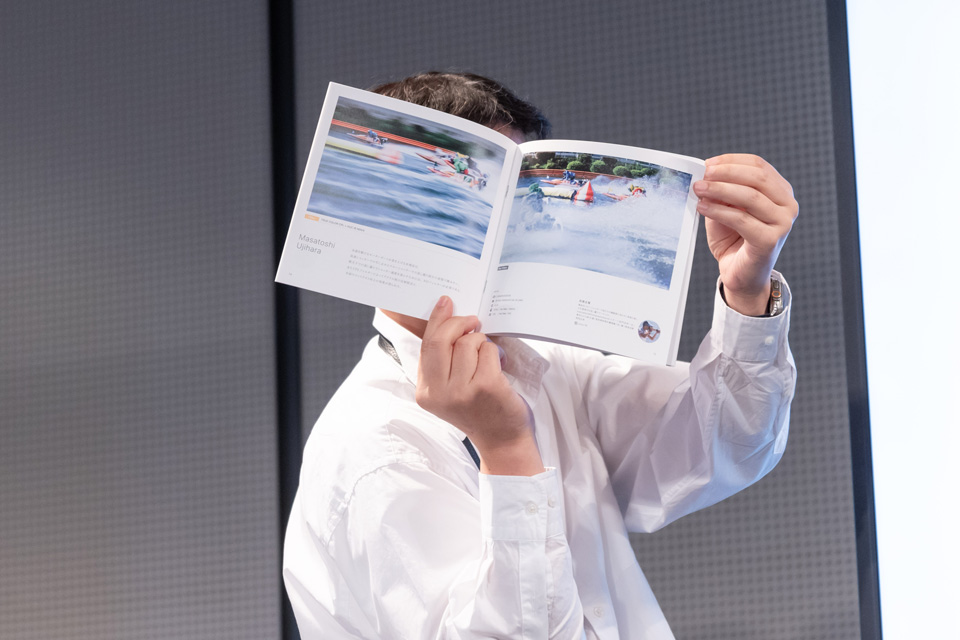
井上「興味を持ってくださった方もいるかと思います。今回、NiSi Filtersさんのブースでは冊子をお配りしています。冊子は左右ページを見開いて見ていただけるとうれしいです。左がフィルターを使ったとき、右にはフィルターを使っていない作例が載っており、見比べることができます。わたしの作例はトークショーでは1枚もお見せしていませんが、冊子には掲載されておりますので見ていただけるとうれしいです。NDフィルターを使っております。ここまで、フィルターを使うことで自分の作風づくりに役立てているということをお話ししました」

井上「さて、ここからはもう少しお聞きしたいことはありますか? 今日ならばどんな質問にも答えてくださると思います。どなたかいらっしゃいますか?」
会場質問「みなさまにとって、写真を撮るということはどのようなことかを教えていただきたいです」
井上「大変ですね。深い話ですね。僕は写真を撮るということに命をもらったような気がします。ダサい話ですが、医学部に4浪して行けず、法学部に行き、法学部で司法試験を失敗し、いま僕には写真しかありません。でも、この写真を撮るということが僕を生かしてくれているなということをすごく感じます。自分がやっていて楽しいことをそのまま仕事にできて、何より写真は自分だけではなくて見てくれる人がいるから、それを楽しんでくださる方々がいるから成り立つんですね。とても社会性の高い仕事に就くことができたなという幸せを感じてシャッターを切っています」
Kogame「わたしはカメラを買ったばかりのときはシャッターを押すことが楽しかったんです。そして娘の成長を撮ることを目的にしていました。ただ、SNSをはじめてからは、SNSでいいねをもらうために撮っている自分がいることに気付き、それがとても嫌に感じてしまったんです。SNSから離れて、国際フォトコンテストのほうに視野を向けるようにしたんですが、International Photography Awardsの審査員から、写真は見た人の心を動かすことができる、行動させることができるという言葉をもらったんですね。それを聞いたときには只見線の冬の写真を出していたのですが、この景色を写真として残すのではなく、自分の子どもや孫が同じ景色を見られるようにしたい、と思ったんです。わたしの写真を見てくれた方が自然保護の活動をはじめるなど行動に繋がってほしい。いまはそれが原動力になっています」
Koichi「ちょっと規模が大きい話なんですけれど、自分はこの宇宙の中の地球に生まれて、その中の日本に生まれて。こうやって令和というすごく良い時代に、自分の好きなカメラを使い写真を撮って仕事にしているなんて、こんな幸せなことはないなと思っています。そして、せっかく日本に生まれて写真を撮っている自分だからこそ、この日本の良さを伝えることができると思っています。便利なことにSNSも発達していて、世界中に作品を簡単に届けられる時代だと思っているので、日本に来たくても来られない人、日本のこの景色を見てみたいなと少しでも思ってもらえるような作品を、世の中に出していけたらいいなという気持ちで撮っています」
井上「そう、つまり自己満足という点ももちろんあるんですが、ただ一方でそれを誰かに見てもらうことで、未来が生まれることに写真の素敵なところはあるのかなと。ひとりではできないところが、むしろ楽しいというところなのかなと思います。さてもうおひとりいきましょう」

会場質問「わたしはまだ飛行機を好きになって1年くらい、カメラを買ったのはまだ2月で、シャッターを切っているだけで楽しいです。みなさんに聞くと、必ず壁があると。シャッターを切っているのが楽しいだけではなくなるとみなさんおっしゃるのですが、そのような壁はどのように乗り換えたのでしょうか」
井上「そう、たしかにシャッターを切っていて辛いときというのもあったような気がするんですよね。僕の場合はすごく自分勝手だったので、何で自分の写真が社会的に評価されないんだと。フォトコンテストでまた無視されたと、本気で思っていました。でも、フォトコンテストだけが写真じゃないんです。家族が喜んでくれたり、友だちが喜んでくれたり、もしかすると1年前の自分といまの自分とを比べて、いまの自分が写真を見て喜んでいるならそれでいいじゃないかと。僕はそういう自己満足で、乗り越えてきたような気がします。あとは仲間でしょうね。価値観の合う仲間がいることで、写真を続けるのが楽しくなるのかなと思います。一緒に出かけるのも楽しいですし、こんなレンズ買ったよ、というような報告を受けて、そして自分はこのフィルターを使ってみたらこんな写真が撮れたとか、機材で楽しみを分かち合うということもできます」
Kogame「わたしの場合は、ずっとひとりで撮ってきました。井上さんがおっしゃったようにフォトコンテストにまったく通らず、自分の写真が悪いんだとずいぶんと悩んだ時期もありましたし、センスがないことに気付かされました。しかし、もっとこういう写真を撮りたいという目標を見つけるようにしました。それに対しどのようなステップでやっていけばいいかを細かく分析し、ひとつずつクリアすることで、目的に到達することができたんです。宣伝になりますが、この後、NiSi Filtersのブースで写真がうまくなる具体的な方法についてトークをします。まさにご質問の答えだと思いますので、ぜひご視聴いただければと思います」
Koichi「わたしは、そのような感情になったとき、そのまま写真に感情をぶつけるようにしてきました。大学のときに写真をはじめた当時は荒川の土手のすぐ下に住んでいたんですけど、彼女にフラれて、めちゃくちゃ悔しくて、泣きながらもとりあえずカメラを持って土手に走って行ったんですね。そうしたら高校生のカップルが仲良く話していて、これもひとつの出会いだなと声を掛けて撮らせてもらって、そのときの写真がいまの僕の名刺のデザインなんです。それが風景の中に人物を入れる作風のきっかけになったのかなと思っていて、その感情のときにしか撮れない表現、気持ちが乗るというのも写真のとても楽しいところだと思うので、壁が現れたときは、素直にその気持ちを写真にぶつけてみるのも手段だと思います」

井上「ぜひ、トークショーの後にはNiSi Filtersのブースにお越しいただいて、実物のフィルターも置いてあるので使ってみてください。オススメなのは、『FS ND』という茶筒の蓋ようにレンズの前にポンと着けることができるフィルターがあるんです。その手触りを試していただきたいです。本日はトークショーにお集まりいただきありがとうございました」
Koichi「ありがとうございました。作風はそれぞれだと思いますが、自分の好きな表現を詰め込むことができるのは、写真の楽しさだと思っています。ぜひ、これからもたくさんの写真を撮り続けていただけたらなと思っています。本日はありがとうございました」
Kogame「いろいろ述べましたけれど、結局は楽しければなんでもいいと思っていて、わたしもいい仲間ができて写真を楽しんでいます。その輪がみなさんにも広がってほしいと考えております。これからも楽しくやっていきましょう。今日はありがとうございました」

